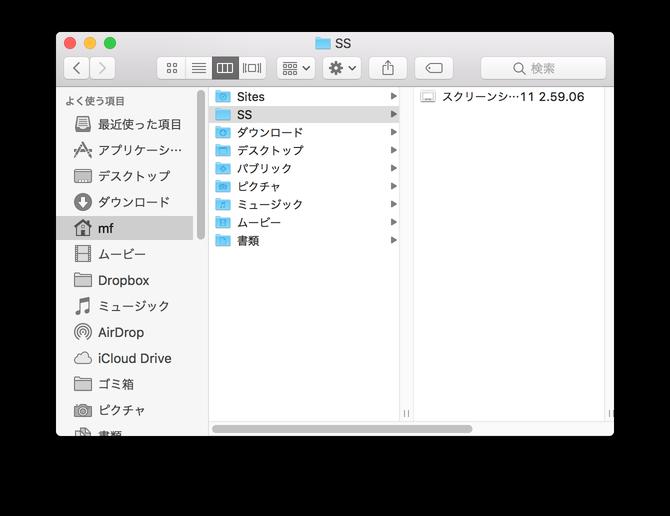経済・IT 日本の住宅設備「デジタル化が進まない」根本原因
「あれば便利かもしれないけど、別になくても困らない」というイメージを持たれがちなスマートホーム(写真:Fast&Slow/ PIXTA)
日本の住宅市場で20年以上前から注目されながら伸び悩んでいるのが「スマートホーム」だ。約10年サイクルでブームが訪れ、すでに多くの住宅会社や家電メーカーが商品化しているのだが、本格普及には至っていない。
コロナ禍で、世界に比べて日本社会のデジタル化が遅れていることが明らかになったが、この分野でも日本はアメリカや中国に比べて出遅れている。そんな「スマートホーム」が岸田文雄首相の目玉政策である「デジタル田園都市国家構想」のなかに盛り込まれた。
日本でもテレワークやネット通販が一気に普及し、マイナンバーカードを使った行政サービス、オンライン授業、遠隔診療も始まった。「住宅」が職場、行政、学校、病院・薬局、小売りなど、あらゆるところとつながるようになり、とくに地方での暮らしを便利で快適にするには「住宅」を起点に、さまざまな地域サービスの利用環境を、デジタル技術を活用して最適化していく必要があるからだ。
すでにスマートメーター(通信機能付き電力量計)の全世帯普及がほぼ完了し、エアコン、給湯器などの住設機器、テレビ、冷蔵庫などの家電製品とインターネットにつながる機器も増えている。はたして日本の「スマートホーム」は、快適で便利な暮らしを実現する生活基盤へとイノベーションできるのか。
スマートホームとはどのような住宅か
「スマートホーム」と聞いて、どのような住宅をイメージするだろうか。ICT(情報通信技術)を搭載した住宅は過去にいろんな名称で商品化されてきたが、これといったイメージがまだ確立していないのが現状だろう。
1990年代前半に日本でインターネットの商業サービスが開始されると、住宅内にネットワークを構築して異なるメーカーの家電製品や住宅設備機器を相互接続しようと、1997年に民間団体「エコーネットコンソーシアム」が設立され、標準通信規格「エコーネット」の開発がスタートする。2001年にIT国家戦略「e-Japan戦略」が始まると「IT住宅」の名称でブロードバンド(広帯域)インターネットの世帯普及が進み出した。
2011年には、地球温暖化など環境問題への対策としてエネルギー使用を効率化する「スマートハウス」が登場。HEMS(家庭向けエネルギーマネージメントシステム)搭載の「ホームコントローラー」を中核に、太陽光発電システム、「エコーネットライト」対応のエアコンや給湯器などを装備した住宅だ。
2017年にアマゾンやグーグルの日本語対応「スマートスピーカー」が登場すると、家電機器などがインターネットにつながるIoT(インターネット・オブ・シングス)技術やAI(人工知能)を搭載した「IoT住宅」「インテリジェントホーム」などが発売された。その後はロボット掃除機や調理器などの「スマート家電」も増えている。
どれも住宅内に設置した家電・住設機器が宅内通信回線やインターネットに「つながる」ことが「スマートホーム」の基本要件であるのは間違いない。
普及が進まないスマート家電
日本ではパソコンの世帯保有率は2020年に70%、スマートフォンは86%を超え、インターネット利用率(個人)も83%に達している(総務省「情報通信白書」2021)。しかし、スマート家電の世帯保有率は7.5%で、過去10年間、ほぼ1桁台にとどまっている。
現時点で「スマートホーム」に対する消費者のイメージは「あれば便利かもしれないけど、別になくても困らない」というものだろう。
2020年6月に発足したスマートホーム普及団体のLIVING TECH協会代表理事の古屋美佐子氏(アマゾンジャパン・オフライン営業本部営業本部長)によると、スマートスピーカー「アマゾンエコー」も「日本ではストリーミング音楽再生の用途で売れている」のが実情のようだ。他には既存の家電製品の赤外線リモコンをまとめて操作できる「スマートリモコン」も売れているが、これも従来の生活スタイルを大きく変えるような利用方法ではない。
しかし、同協会が実証実験のために建てたスマートホームで、さまざまなスマート家電を連携して利用できるサービスを体験したモニター家族からの評価は高いという。
「住宅の電気使用量をHEMSで“見える化”しても、利用者はすぐに飽きて見なくなるのではないかと懸念していたが、意外とよく見られていることがわかった」。約10年前にスマートホームを発売した大和ハウス工業で長年、同分野の研究を続けてきた総合技術研究所主任研究員の吉田博之氏も利用者の潜在的ニーズは高いと見る。
課題は、スマホやパソコンのように、簡単にネット環境につながってサービスを利用できること。家電・住設機器とサービスの両方が、消費者が利用しやすい手頃な価格で提供されることだろう。
日本では標準通信規格「エコーネットライト」が開発され、同規格搭載機器の累計出荷台数は2020年に1億台を突破した。しかし、家電メーカー各社は当初、競合製品がつながらない「囲い込み戦略」を展開し、相互接続がなかなか進まなかった経緯がある。
一方、アメリカではIoT機器をクラウドサーバーからインターネット経由で操作できる環境が整うと、WebAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)という技術を使って、異なるメーカーのクラウドサービスを連携するIT系ベンチャー企業が現れた。
2010年に開発された連携プラットフォーム「IFTTT(イフト)」と呼ばれるサービスを利用すると、アマゾンやグーグルのスマートスピーカーから、アイロボットの掃除機やフィリップスの照明など、異なるメーカーの機器を操作できる。「つながる」ことで「スマートホーム」の普及が始まったわけだ。
日本でも、WebAPIを利用した「スマートホーム」は2017年頃から登場する。パナソニックでも、HEMSトップシェア(同社調べ)のホームコントローラー「AiSEG(アイセグ)2」でWebAPIによる他社連携サービスをスタートし、オープン戦略へと転換。2018年には標準通信規格「エコーネットライト」搭載機器を対象としたWebAPIのガイドラインも策定・リリースされた。

WebAPIによる他社連携はなぜ進まないのか
「パナソニックは2年前の発表で、AiSEGでホームIoTのデファクト(事実上の標準)をめざすと表明したが、残念ながらWebAPI連携できる他社の機器はほとんど増えていない」
パナソニックのAiSEGを採用している住宅供給会社からは落胆の声が聞かれる。
エコーネットのWebAPIも、2021年9月に関西電力のスマホアプリから三菱電機のエコキュートを遠隔操作するのに使われたのが初めてだ。長年、エコーネットの普及に取り組んでいる神奈川工科大学の一色正男教授も「各社には採用をお願いしているのだが……。実際に採用した事例が出てきたので、これから普及するのではないか」と期待するが、先行きは不透明だ。
「最初は国内ITベンダーのWebAPI連携サービスを検討したが、先方が事業撤退することになった。IFTTTも当初は無料サービスだったが、2020年9月に突然、有料プランが発表され、無料で使える機能は大幅に制限された。外部のWebAPIを利用してサービスを提供するのはリスクもある」。大和ハウス工業の吉田氏もそんな見方を示す。
なぜ、WebAPIによる他社連携は進まないのか――。
その背景をパナソニックに聞くと「APIは有料で広く公開している。それを使って接続するかどうかは相手側の政策的な判断だ」との答えが返ってきた。住宅会社の中には、ホームコントローラーで得た電気使用量や温度などのデータを使って住宅性能をアピールして営業活動に役立てている企業もあるというが、そのデータを提供するのも有料だ。
日本の大手家電メーカー各社は、従来の家電・住設機器のハード単品売りから、ハードから得られるデータを収益化する高付加価値なビジネスモデルへの転換を目指している。確かにスマート家電や住設機器とAPI連携して儲かるサービスを提供できる見込みがあれば、有料でもつなげようという企業は出てくるだろう。
昨年8月に積水ハウスが、パナソニックのAiSEG2を装備したスマートホームサービス「プラットフォームハウスタッチ」の提供を開始した。スマホで、玄関施錠、エアコン、照明、湯はり、床暖房、窓シャッターの操作ができるほか、温湿度センサーによる熱中症アラートや火災警報器鳴動の通知機能がある。これらを利用するのに機器の初期投資に加えて、月額2200円の使用料がかかる。まだ発売して半年で販売実績は公表されていないが、「好調」という話は聞こえてこない。
アメリカでもスマートホームサービスで成功しているのはベンチャー企業がほとんどだ。はたして日本の大手家電メーカーが彼らの重たい間接コストを抱えながら収益化をめざしても、広く一般家庭に普及するようなスマートホームサービスを生み出すことができるのだろうか。
「技術的にはすでに実現可能な状況」だが…
「スマートシティやスマートホームで提供が検討されているサービスのほとんどは、技術的にはすでに実現可能な状況にある。問題は消費者が利用したいと思える料金で提供するための『共助』のビジネスモデルを実現できていないことだ」。デジタル庁で国民向けサービスグループの責任者で、デジタル田園都市国家構想も担当する村上敬亮統括官は、そう指摘する。
村上氏は2年前に日本版スマートシティ「スーパーシティ構想」の立ち上げにも関わり、スマートシティ実現のための「データ連携基盤」の整備に取り組んできた。「スマートホーム」はスマートシティを構成する重要アイテムであり、スマートシティで提供される行政、教育、医療、交通・物流などのサービスの多くは住宅を中心に利用されるものだ。
戦後、日本が高度経済成長を遂げたのは、道路や鉄道などの社会インフラ整備は「公助」、農業、エネルギー、製造業などは民間事業者による「自助」が分担する経済モデルがうまく機能したからだ。
しかし、デジタル社会において「民間企業が協力してコストや利益をシェアして事業を展開する『(日本版エコシステムとしての)共助』のビジネスモデルを確立して広げていく必要がある」と村上氏は強調する。それが実現できなければ、GAFAM(グーグル、アップル、フェイスブック=現・メタ、アマゾン、マイクロソフト)のような巨大IT企業に市場を支配される懸念があるからだ。
デジ庁では、スマートシティ実現のための「データ連携基盤」を開発して提供する準備を進めている。この基盤をスマートホームのサービス連携にも活用し、デジタル田園都市国家構想のなかで地方・中小の生活・産業の変革につなげていく。
その仕掛けを所管しているのが、経済産業省情報経済課のスマートライフのチームであり、その担当の一人がアーキテクチャ戦略企画室の和泉憲明室長。もともとは博士号(工学)をもつ産業技術総合研究所(産総研)の研究員で、2017年にIT戦略立案のために経産省に移籍した人物だ。
「スマートホームの実現により、生活者の需要に関する情報、消費財や住宅メンテナンスなどのライフサイクル情報を構造化して分析可能とすることで、製品・サービスの新たな連携・エコシステムが構築できるのではないか、という期待がある」
インターネットの世界で「情報の構造化」を実現して巨大企業へと成長したグーグル、それらの情報を分析しレコメンデーション(推薦)機能によって流通市場を制覇したアマゾン。この2社が行った取り組みをスマートホームの世界で実現しようというわけだ。
スマートホームのアーキテクチャ(構造体系)を構築するうえで、「データ連携基盤」は国が用意したとして、「共助」のビジネスモデルはどう構築していくのか。
三菱地所が立ち上げたスマートホーム
「日本でスマートホームが普及しないのは、ユーザーが使いにくいうえに、住宅供給会社としても安心して採用・提供できるサービスがないから」。三菱地所は昨年11月にスマートホームサービス「HOMETACT」を独自開発し、賃貸マンション「ザ・パークハビオ麻布十番」(住戸数106戸)に導入した。
従来のスマートホームサービスは、メーカー横断での機器連携が進まず、ユーザーは複数アプリをバラバラに利用するしかなかった。加えて設置・設定もユーザー任せになるケースが多く、コールセンターや緊急対応などのサービスが充実していない。その結果、住宅供給会社としてはなかなか採用しにくかった。
三菱地所では、そうした状況を打破すべく、アメリカのベンチャー企業YONOMIのAPI連携技術を導入し、リンナイ、スマートロックのライナフ、赤外線コントローラーのLiveSmartなど多くの企業の協力を得てIoT連携基盤を開発し、ビックカメラグループとの協力による設置・設定、コールセンター機能をパッケージ化して「HOMETACT」を立ち上げた。
「これまでさまざまなスマートホームサービスと連携してきたが、三菱地所の開発スタンスは他社とは違っていると思う。当社製品が採用されるメリットだけでなく、新しいサービスを開発するために必要なデータ提供などに応じることにも魅力を感じた」(リンナイ情報システム部部長・山本浩樹氏)
三菱地所は自社の賃貸マンションから同サービスを導入したが、将来的には他の住宅供給会社にも同サービスを提供していく計画だ。「HOMETACTはIoT連携に積極的な参加企業と協力しながらエコシステムを構築していく」(三菱地所の住宅業務企画部主事・橘嘉宏氏)と、まさに「共助」のビジネスモデルを構築したうえで、メーカーや住宅供給会社を巻き込みながら、集合住宅を中心に日本の住宅市場にスマートホームを定着させていく戦略だ。
日本社会がDXできるかどうかの試金石に
これまで「スマートホーム」を普及するために、2017年に東急グループ、パナソニック、美和ロックなどが設立した団体「コネクティッドホームアライアンス」など、さまざまな取り組みが行われてきた。
しかし、「いざデータ活用のあり方などを検討しようとすると、議論が前に進まなくなる」(アライアンス参加企業幹部)と、期待される成果を出せていないのが実情だ。
はたして日本の「スマートホーム」は「共助」のビジネスモデルを構築し、飛躍することができるのか。まさに日本社会がデジタルトランスフォーメーション(DX)できるかどうかの試金石になる。